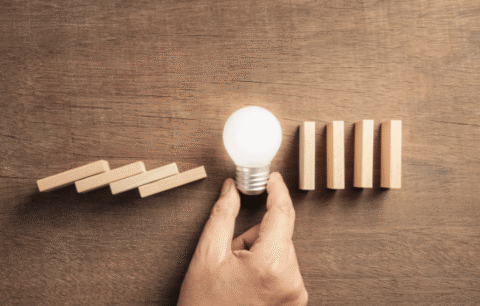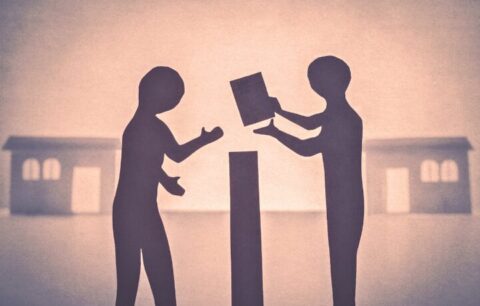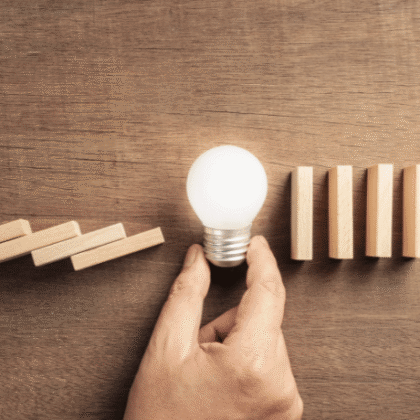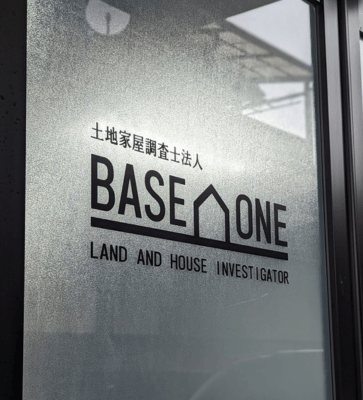筆界確認書とは?境界トラブルを防ぐための基礎知識と実例【Q&Aで徹底解説】
はじめに
土地を所有している方、または購入・相続を考えている方からよく寄せられる質問のひとつが「境界ってどこ?」というもの。
実は、境界をしっかり確認しておくことが、将来のトラブルを防ぐ最大のポイントです。
今回は、土地家屋調査士が現場でよく聞かれる質問をもとに、筆界確認書の基本から作成の流れ、実際の事例までをQ&A形式で分かりやすく解説します。
Q1. そもそも「筆界(ひっかい)」って何ですか?
A. 「筆界」とは、登記上で定められた土地と土地の境界線のことをいいます。
これは法務局に登録された公的な境界であり、土地所有者同士で勝手に変更することはできません。
一方で、実際に使っている塀やブロックの位置(=占有界)が筆界とズレていることもあります。
このズレを放置すると、将来的にトラブルになることがあるため、正しい境界の確認が重要です。
Q2. 「筆界確認書」とはどんな書類ですか?
A. 筆界確認書とは、隣地の所有者と境界線を確認し、双方で同意した内容を文書にしたものです。
土地家屋調査士が測量を行い、現地で立会いを実施した上で、「ここが筆界です」と合意した境界点を明確に記録します。
この書面があることで、
- 将来の境界トラブルを防げる
- 売買・相続の際にも安心
- 登記や分筆の根拠となる
などのメリットがあります。
Q3. どうやって筆界確認書は作られるの?
A. 以下のような流れで作成します
① 現地調査
法務局に保管されている資料や、その他の関係官庁の資料など、さまざまな筆界に関する情報を収集したうえで、現地の確認を行います。
その際、境界標識(境界プレートやコンクリート標)などの有無を確認し、次の測量作業を円滑に進めるための事前調査を実施します。
これらの情報をもとに、より正確で効率的な測量計画の立案に活かします。
② 測量
調査内容を踏まえ、現地の状況を正確に測量します。
必要に応じて、隣地所有者の立ち入り許可を得たうえで隣地の状況も測定することがあります。こうした手順を経ることで、正確な筆界を導き出すことが可能となります。
③ 立会い
測量調査の結果を踏まえ、事前の準備を整えたうえで、当事者間による筆界の立会を実施します。
立会の際には、過去の筆界に関する資料を持ち寄って確認したり、これまでの経緯を共有したりしながら、さまざまな背景を総合的に判断し、筆界について協議を行います。
④ 同意・署名
立会の内容を図面に反映し、当事者双方が署名・押印を行います。
同一内容の書面を2通作成し、それぞれが保管するのが一般的です。
こうして書面として残すことで、将来的な境界に関する紛争を未然に防止することができます。
立会いは通常5分〜30分程度。(あくまで目安です)
双方の合意が得られれば、その日のうちに完了することもあります。
Q4. 筆界確認書を作るタイミングはいつ?
A. 主に以下のようなタイミングで作成します。
- 土地の売買や相続をする前
- 分筆登記や地積更正登記などをするとき
- 建物を建てる前に境界を明確にしたいとき
- 隣地との境界杭がなくなってしまったとき
特に相続や建替えの前に確認しておくと、後々のトラブルを未然に防げます。
Q5. 筆界確認書がないとどうなるの?
A. 将来、次のようなリスクが発生する可能性があります。
- 隣地との境界争いが発生
- 建築確認申請が通らない
- 相続登記が遅れる
- 土地の売却価格が下がる
特に「昔の塀が境界」と思い込んでいたケースで、実際は登記上とズレていた…という相談が非常に多いです。
Q6. 費用や期間はどれくらいかかりますか?
A. 土地の形状や測量の難易度、筆数、隣地の数、関係者の人数などによって費用や期間は異なりますが、一般的な住宅地の場合の目安は以下の通りです。
費用:10万円〜(条件により変動します。あくまで目安です)
期間:2〜4週間程度(隣地の協力状況によって変動します)
なお、官民境界(道路や河川との境界)を含む場合は、行政との協議が必要となるため、通常よりも期間が長くなることがあります。
Q7. 隣の人が遠方にお住まいであったり、既に亡くなられている場合などは?
A. そのようなケースでも、土地家屋調査士が対応可能です。
- 所有者が遠方にいる場合 → 郵送や写真で説明
- 相続登記が未了の場合 → 職務上請求により相続人を調査
調査士が中立的な立場で調整を行うので、無理なく法的に正しい手続きを進められます。
Q8. 実際の現場でのトラブル事例はありますか?
A. はい、代表的なケースを2つ紹介します。
事例①:古い塀が実際の境界より内側にあったケース
登記図では境界が30cm外側にありましたが、筆界確認書を作成し、
「塀は現況利用」「筆界は登記上の位置」と合意。
将来の売却時にもスムーズに手続きが行えました。
事例②:相続前に境界を確定してトラブル防止
兄弟で相続する前に筆界確認を行い、
のちの分筆登記・相続登記が円滑に完了。
「書面にしておいて本当によかった」と感謝の言葉をいただきました。
Q9. 自分で筆界確認書を作ってもいいの?
A. 法的には可能ですが、おすすめできません。
筆界確認書は「測量データ」「過去の筆界資料などの読み取り技術」「登記記録」「現況」の要素が一致して初めて正確に作れます。
この調整を誤ると、後にトラブルや登記拒否の原因になることも。
専門知識を持つ土地家屋調査士に依頼するのが確実です。
Q10. 最後に、境界トラブルを防ぐためのポイントは?
A. 以下の3つを意識してください👇
1. 「今は問題ない」うちに確認する
2. 筆界確認書を文書として残す
3. 専門家(調査士)と一緒に記録を残す
トラブルが起きてからでは遅いので、「安心を形にしておく」ことが大切です。
まとめ
筆界確認書は、土地の境界の証明書ともいえる大切な書類です。
売買・相続・建築など、どんな場面でも「境界が明確であること」は大前提。
不安を感じた時が、確認のベストタイミングです。
専門の土地家屋調査士に相談し、安心して土地を管理しましょう。
土地家屋調査士法人 BASE ONE(旧 ハヤシ登記測量事務所)
本社:〒603-8838 京都府京都市北区大宮田尻町9番地4
支社:〒603-8826 京都市北区西賀茂坊ノ後町19-2 ハウゼ西賀茂105号室
営業時間:平日 9:00~18:00(定休日:土日祝)
TEL:075-494-5135
FAX:075-494-5130