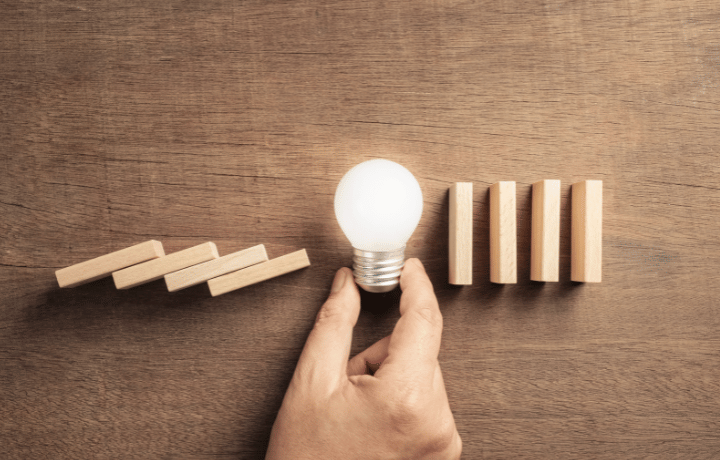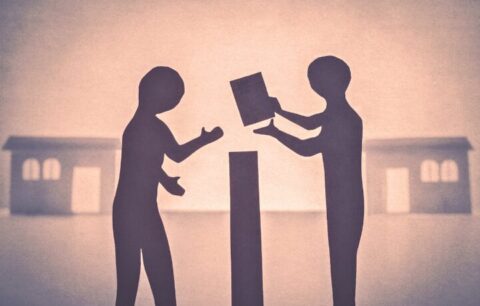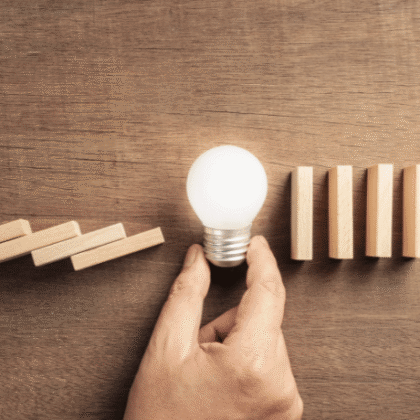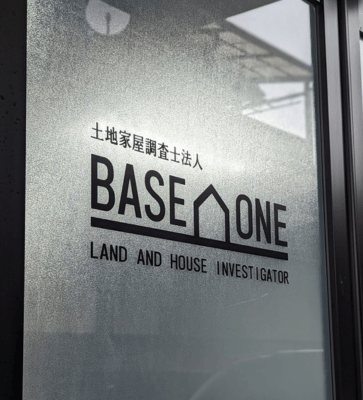よくある土地境界トラブル事例と解決方法 〜土地家屋調査士が解説〜
土地や建物を所有するうえで避けて通れないのが『境界』の問題です。
境界は不動産の価値や利用に直結する重要なラインであり、誤解や思い込みから隣人とのトラブルに発展するケースが少なくありません。
この記事では、実際によくある土地境界トラブルの事例をまとめ、さらに解決に向けたポイントをわかりやすく解説します。
相続や不動産売却を考えている方、隣地との関係で不安を感じている方はぜひ参考にしてください。
1.よくある土地境界トラブル事例
① 境界線の認識の違い
「ブロック塀の中心が境界」と思っていたが、実際は外側だった
測量図と現況に◯cm以上のズレがあり、長年の思い込みでトラブルに発展
▶長年問題が表面化しなくても、売却や相続の際に境界が不明確だと大きな障害になります。
② 境界標(境界杭)の紛失・移動
工事中に境界杭が動かされ、元に戻さなかった
境界移動の合意はあったが、正式に境界標が移設されず訴訟に発展
▶境界杭は土地の根拠となる重要な証拠。
工事前後の写真撮影や土地家屋調査士と共に立会いをすることでリスクを減らせます。
③ 越境物(屋根・雨どい・樹木)のはみ出し
屋根や庇が隣地に越境
樹木の枝や根が敷地を越えて侵入
▶民法234条では、建物は境界から50cm以上離して建てる義務があります。
民法第234条
建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
ただし、慣習によるときは、この限りでない。
違反している場合、撤去や補修が求められる可能性があります。
④ 隣人が協力してくれない
境界確認の署名・押印に応じてもらえない
本人は納得していても、相続人が反対して書類が進まない
▶境界確定はお互いの合意が不可欠。
不仲や不信感があると、手続きが長期化します。
⑤ 相続や不動産売却で発覚するケース
相続した土地を売却しようとしたら測量図と現況が違う
境界が不明確で、売買契約そのものが進まない
▶境界が未確定だと売却価格が下がったり、取引が成立しないリスクがあります。
⑥ 第三者の不正介入
境界の知識に乏しい第三者が間に入り、どちらか一方に偏った主張を通してしまう
公平性を欠いた対応により精神的な負担を強いられた
▶専門家選びは非常に重要です。
不安がある場合は、土地境界の専門家である土地家屋調査士へ相談することが最も有効です。
2.境界トラブルを防ぐ・解決するためのポイント
| トラブルの種類 | 解決方法の例 |
| 境界線の認識違い | 正確な測量・境界確認書の作成 |
| 境界杭の紛失・移動 | 土地家屋調査士による復元、工事前後の記録 |
| 越境物の問題 | 覚書の締結、撤去・補修 |
| 隣人が非協力 | ADR(裁判外紛争解決)、筆界特定制度 |
| 相続・売却時の発覚 | 事前に測量を行い境界を確定 |
| 第三者の不正介入 | 土地家屋調査士に依頼 |
3.まとめ
土地境界トラブルは、小さな誤解から大きな問題に発展する可能性が高いものです。
特に相続や売却の場面では、境界が不明確なだけで取引が止まることもあります。
境界の不安を感じたら、早めに土地家屋調査士へ相談することが最善の予防策です。
土地家屋調査士法人 BASE ONE(旧 ハヤシ登記測量事務所)
本社:〒603-8838 京都府京都市北区大宮田尻町9番地4
支社:〒603-8826 京都市北区西賀茂坊ノ後町19-2 ハウゼ西賀茂105号室
営業時間:平日 9:00~18:00(定休日:土日祝)
TEL:075-494-5135
FAX:075-494-5130